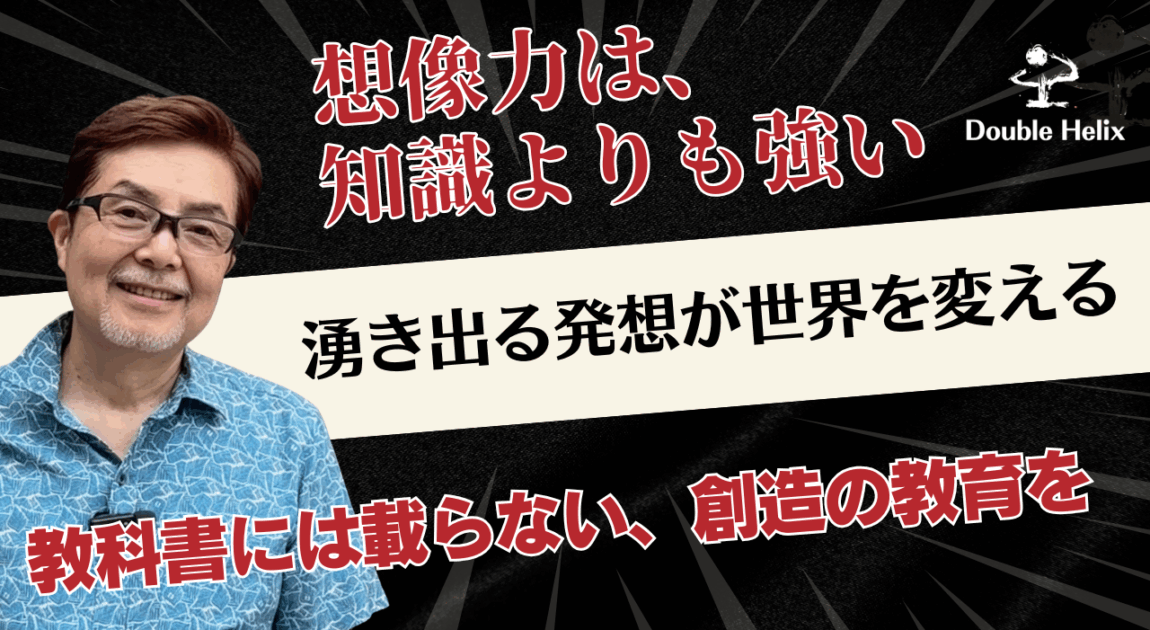創造力が教育を変える ― Double Helix: Professional Development 特別講義
教育の現場に“創造力”を
「想像力は、知識よりも重要である」
アインシュタインのこの言葉を、現代教育の文脈で体現する人物がいます。
ネパールのModern Kanya multiplle大学所属教授であり、
国連にも研究が掲載される科学者・飯島謙一博士。
博士は40年以上にわたり、環境科学、経営学、発酵学といった分野を横断しながら、
「創造力こそ教育の核心である」と語り続けてきました。
Double Helixでは今回、博士の特別講演を 「Professional Development」 の視点から取り上げ、
教育における“創造的思考”の意義を再考します。
知識ではなく「湧き出す力」を育てる
飯島博士が繰り返し語るのは、知識と創造力の決定的な違いです。
知識は、学校や本から「外から与えられる」もの。
一方で、創造力は「内から湧き出すもの」であり、
それを鍛える教育こそが、社会の未来を築く鍵になると博士は説きます。
「創造とは、まだ存在しないものを形にすること。
それができる子どもを増やすことが、教育の使命だと思います。」
この言葉は、教育者自身の“学びの原点”を問い直すメッセージでもあります。
成績1と2の少年が、教授になるまで
博士の人生そのものが「創造的教育の実践例」です。
小学校時代、成績は“1と2”。
勉強が苦手で、教室の外で自然や虫に夢中だった少年が、
やがて科学者となり、大学教授として教壇に立つ。
その背景には、「見えない世界を見ようとする好奇心」がありました。
博士は言います。
「縁の下のアリ地獄を観察していた時間が、
いまの研究の原点になっています。」
これは、点数や偏差値を超えた“教育の希望”を象徴する物語です。
科学的発想が社会を変える
博士は研究者であると同時に、実業家でもあります。
ウィークリーマンション、銚子丸、楽天生命
その誕生の裏には、「研究費を生み出すための創造力」がありました。
このエピソードは、「学び」と「社会の実装」が直結していることを教えてくれます。
教育現場においても、“考える→試す→社会に出す”という循環型の学びが、
これからのキャリア教育に欠かせない要素になるでしょう。
逆境を超えて、新しい教育を創る
博士は数年前、がんを宣告されました。
しかしその病床で生まれたのが、「KHシステム」という新しい経営モデル。
“働けなくても社会に貢献できる仕組み”を考案し、
いまも多くの企業に導入されています。
それはまさに、「制約があるからこそ、創造が生まれる」という教育哲学。
この考え方は、教職員の働き方やキャリア形成にも通じるヒントです。
世界に広がる創造力教育
現在、博士はネパールやスリランカで、微生物を活用した環境・医療教育にも取り組んでいます。
「コーヒーで血糖値を下げる」研究は現地で注目され、
映画化プロジェクトも進行中です。
科学・社会・教育が一体となる博士の活動は、
まさに “Double Helix(=二重らせん)” のように、
人間の知と創造性が絡み合う象徴と言えるでしょう。
🎥 特別動画:創造力は知識を超える
『Double Helix: Professional Development – Special Session』
本記事では、博士の講義を収録した動画を公開しています。
📺 ▶ 創造力は知識を超える(動画はこちら↓)
本講義では、
教育現場の先生方、保護者、そして未来の教育リーダーに向けて、
「創造力がどのように子どもの可能性を拓くのか」が語られています。
おわりに
Double Helixは、これからも多様な学びのかたちを発信していきます。
飯島博士の講義は、教師・保護者・地域社会のすべてに問いを投げかける内容です。
次回以降も、さまざまな視点をテーマに、
実践的なProfessional Developmentプログラムをお届けします。